その意味を強く意識して、チームワークをもって作品のレベルを上げること。中でも特に仲間ということについて、嫌いな人間を好きにならなくてもいいですが、チームワークを組める人間関係を大切にすることを伝えつづけてきました。」と言います。
ジャンルに関係なく、どんな仕事もベストを尽くしてスポンサーやお客様に喜んでいただけるように相手を理解し、提案し、努力を続けていくABCが、ここから始まりました。
四谷にて有限会社アートブレーンカンパニー設立。
本社を中野新橋へ移転。
音響、照明器材を扱う会社として、有限会社システムアートを設立。
中野区弥生町に自社ビルを建設。事務所兼倉庫とする。
株式会社アートブレーンカンパニーへ組織変更。
1976年は、有限会社アートブレーンカンパニーが四谷にて設立された年です。
その社名について、森田会長は「Artとは、もちろん芸術です。感性を磨き個性を伸ばし、一流を目指すこと。Brainとは、頭脳・知能です。頭を使って考えぬき、社会性を高めてお客様に喜んでいただくこと。Companyとは、仲間です。続きをみる
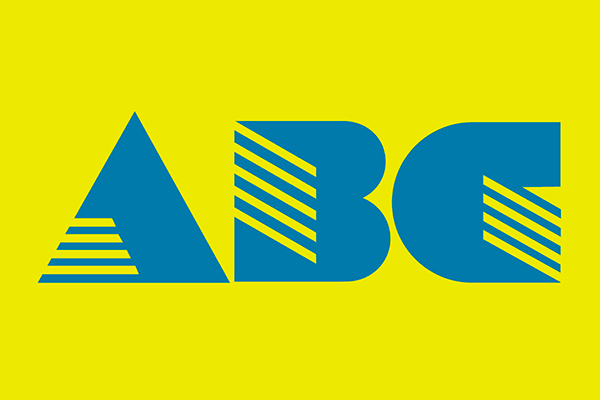
誰もやらないんだったら、私たちが最初にやる。
それは、1977年のこと。先日他界されたショーケンこと萩原健一さんのコンサートが東宝の撮影所で開かれました。そこで、おそらく照明では初めての試みが行われたのです。森田会長は当時を「ABCは、批判されるようなことをいっぱいやってきましたね(笑)。続きをみる

当時は“目つぶしライト”と呼ばれていた客席に向かってのライトは、お客様を冒涜しているとまで言われましたから。」と振り返ります。「でも、せっかく大きなライトがあるんだから、真後ろに置いてエンディングでドカーンと点けて、そのまま光の中をショーケンがステージから降りていくという演出をしたんです。お客様からのアンケートには“雲の上を歩いているみたいに見えて、きれいだった。”という声が、いっぱい書かれていて。業界の人たちの方が、むしろ保守的だったんですよね。」誰もやらないんだったら、私たちが最初にやる。いつも先駆者としてABCが始めたことが、今ではあたりまえのことになっている事例が、たくさんあるのです。
「裏側の話だけどね…」と謙遜する森田会長に話してもらったのは、1966年に来日したビートルズの記者会見の照明の話。その会場になった当時の東京ヒルトンホテルの調光室にいたのが、まだ学生だった森田会長でした。「当日もスター・ヒル・クラブでの仕事があったのですが、いつもより警備が厳しくて。続きをみる
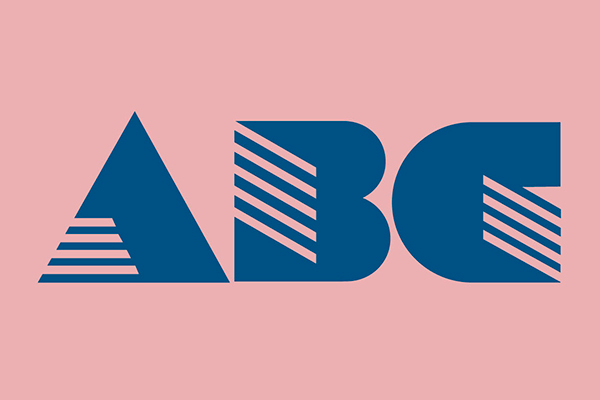
社員じゃない私が中に入るのは大変でしたが、ホテルのセキュリテイの担当者が出てきてくれました(笑)。仕込みから手伝って、ほんの少しアドバイスをさせてもらっただけですが、調光室から見ていた記者会見のことは、よく覚えています。メンバーたちが入ってくる前に明かりのイメージを話して、実際にフェーダーを上げたのはエンジニアの方でした。」と話す森田会長。日本のエンターテインメントの歴史的な瞬間に関わっていたこと。それを自分からは自慢話にしないこと。そこにも、確かなABCらしさが見られます。
お客さまのために、私ならこうやる。
森田会長はABC創業の前から器材・機器を大切に扱うことに、こだわりつづけてきました。続きをみる
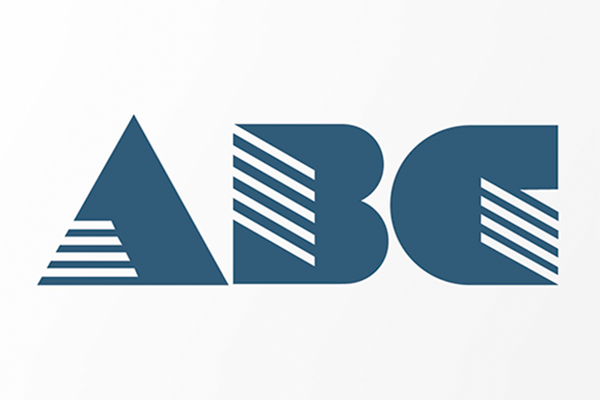
「業界の古い考え方の中には“器材は傷ついてもいいんだ”というものがあったのですが、私はそれが嫌だったんです。まだプラダンもなかった時代で、器材を守るためにメーカーにダンボール箱だけ売ってもらえないかと交渉しても最初は断られました。“前例がない”って。でも、例えばフロアのショーでは、器材や配線はお客さまからも見えるわけで、それを大切に扱うことは、あたりまえのことだと思っていました。森田さんのとこは器材がきれいだからって、わざわざショーの仕事をうちに回してくれたりする人も出てきたのです。」
その姿勢は、業界へと広まっていくことになります。「例えばハイエースの荷室に一つの劇場分の器材を載せる時、箱に入れようとしても全部は入らないとしたら、裸の器材を傷つけながらガチガチに積み込むのと、丁寧に箱に入れて2台で運ぶのと、どちらが本当の意味で経済的で信頼につながるか。それは自分たちの仕事のレベルを上げていくことなんですよね。まだ駆け出しの頃、ある大道具の職人さんに“のこぎりを貸してください”と言っても、貸してもらえなかった。“商売道具は、俺たちの命みたいなものだから”って。なるほど、それが私たちにとっては、器材なんですよね。」
きれいな手で、きれいな器材で、きれいな配線で、きれいな仕事をする。ABCの土台とも言えるこの企業姿勢は、近年の現場でもブラジル人のDJから「配線ケーブルの美しさが素晴らしい!」と言われるなど、私たちの手に受け継がれているのです。

「私に自分の会社を作ったらいいじゃないかと言ってくれた恩人が、東阪企画の故・武井泉会長で。その武井さんから、あるファッションショーの仕事で相談されて、アイデアを出してみてと言われたので、じゃあ花道の両側に出たばっかりのハロゲンのストリップライトをズラッと並べてみたらどうですかと提案したんです。」続きをみる

ショーの花道の両側に、ストリップライトを並べてみた。
ABCのファッションショーの仕事の始まりを、森田会長は「私に自分の会社を作ったらいいじゃないかと言ってくれた恩人が、東阪企画の故・武井泉会長で。その武井さんから、あるファッションショーの仕事で相談されて、アイデアを出してみてと言われたので、じゃあ花道の両側に出たばっかりのハロゲンのストリップライトをズラッと並べてみたらどうですかと提案したんです。
そうしたらおもしろがってくれて、よし!自分の演出料を全て渡すからやってみてくれと(笑)で、やってみたら大成功で、お客さんから拍手が起きました。森田だったら、おもしろい提案をするだろうと思ってくれていたんですよね。それからしばらくは、花道にストリップライトを並べるのが流行ってしまいました。」と話します。
「はじめは小さいクライアントの仕事ばかりしていましたが、ひとつひとつ反響を呼びながら仕事が増えてきて、機材も増えてきて。ファッションショーの花道で使ったストリップライトなんか、1本の長さが1,800あるんですよ。それが20本くらいあって、業界にもあまり無かった最新のライトを、いつまでも親戚の家に置いておくわけにもいかず、倉庫を借りなきゃと見つけたのが、やがて本社を創業する場所になった四谷の本塩町の半地下みたいな事務所でした。」
みんながバカにしていた仕事も、結果を出せば評価になる。
「ファッションショーの仕事を始めた頃、あんなのは電気屋の仕事だって、みんなバカにしていたんですよ。ホテルのフロアとかじゃなくて、劇場でやる仕事が自分たちの仕事だと思ってたんですよね。でも、ホテルでやる時も、例えば穴が不規則に並んでいるならそこからバトンを下げて全部の照明を付けて。それも評価されましたね。」
昔からこうだからではなく、自分にできることを考えてきた。
「ファッションショーのヘアメイクの担当者とは、しょっちゅう喧嘩していました(笑)。
私が関わるまでのファッションショーって、みんながオバケみたいな化粧で。クレームを入れたら『昔からこうだから』って言う。いや、昔はそうかもしれないけれど今は照度も上がっているし、わざわざモデルを汚く見せたいのかと。ナチュラルに変えてくれと言って大ゲンカになったけど、リハーサルの時に見てもらったら納得してくれて、変えてくれましたね(笑)。」
今までにない反応を、お客さまがしてくれて、次につながる。
「プロとして、先輩から言われるままではなくて、照明だってメイクだって、自分の仕事を真剣に考えなくちゃいけないんですよね。私自身は、ファッションに特化して仕事をしてきたつもりはなく、基本スタンスは『来る仕事は拒まず』でやってきたつもりです。今までにない反応をお客さまがしてくれたからこそ『次回もよろしくね』となる。その繰り返しでした。」
「モデルをきれいに見せたい、洋服をきれいに見せたい、色柄だけじゃなくて素材もちゃんと見せたいというのが私の発想でした。」続きをみる
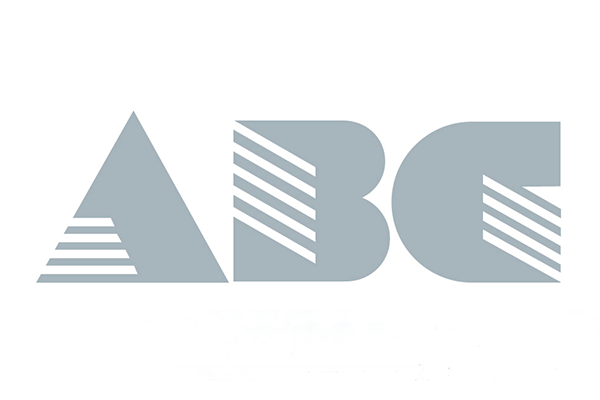
モデルをきれいに見せる、洋服をきれいに見せるという発想で。
森田会長は話します。「以前のファッションショーの照明は前明かりで、とにかくドカンと明るくすればいいんだという世界だったんです。それを私は、花道に沿ってライトを入れて、正面からもサイドからも押さえの光を入れて、モデルが出てきた瞬間にフワッと浮き上がるような明かりにしてみたんです。これ、ファッションショーだからじゃなくて、コンサートでも同じなんですよね。登場した瞬間から、それなりに見える明かり、ただそれだけのことです。モデルをきれいに見せたい、洋服をきれいに見せたい、色柄だけじゃなくて素材もちゃんと見せたいというのが私の発想でした。」
やるんだったら、お客さんに拍手させたいという気持ちでした。
「他の人がやらなかったから、自分でやったんです。始めた当時はファッションショーっていうのは、みんなはやりたがっていませんでしたからね、この業界では。誰に教わったわけでもなく、自分なりに考えてやってきました。私がやるんだったら、お客さんを喜ばせたい、拍手させたいっていう、その気持ちだけでしたね。」
「お客さんの反応がいい時は、やっぱりものすごく気持ちいいです。調光室から顔を出して、私がやりました!このシーンは私が作ったんです!って言いたくなるくらいの気持ちになります。スポンサーさんより観客の皆さんが盛り上がってくれると、やった!という感じになってね。」
この程度でいいだろうっていう言葉が、もう大っ嫌いでした。
「私は、この程度でいいだろうっていう言葉を吐く人間が大っ嫌いで。もう時間がないから、ちゃんと決めてもいないのに次へ行こうとか、この程度でいいという言葉を聞くと、ブチ切れていましたね。
その程度でいいんだったら、次回から、その程度でいいところに頼んでくれって。
私は、その程度で手を打つ仕事は絶対にしたくありませんでしたから。」
「やっぱりぶつかるっていうのは、お客さんを喜ばせようと思っているからなんですよね。
演出家は演出家で、そのショーを良くしたいと思っているんです。そこに違いがあれば、当然ぶつかることになる。私も納得しないし演出家も納得しない時には、私が折れた後でも飲んだ時に思い出して、あそこはやっぱりこうするべきだったと、結局ぶつかっちゃう(笑)。」
10人いたら、10通りの明かりがあっていいと思います。
「感覚ですから、どんなに頑張っても全く合わない人って、いるんですよ。その人が納得できて喜んでくれるような明かりを作っても、私自身は煮え切らない気持ちになったりして。それは感性の違いだから、しょうがない。そういう人には別なスタッフを紹介してみて、そうすると、そのスタッフの感性と不思議なくらい合ったりするんですよ(笑)。10人いたら、10通りの明かりがあっていいと思っています。」
三越でのフロアショーがファッションデザイナーのオスカー・デ・ラ・レンタとの出会いだったと、森田会長は話します。続きをみる

三越の仕事で、オスカー・デ・ラ・レンタに指名される。
三越でのフロアショーがファッションデザイナーのオスカー・デ・ラ・レンタとの出会いだったと、森田会長は話します。「三越でのオスカー・デ・ラ・レンタの仕事を本人が気に入ってくれて毎年やっていたのですが、ある時に本人の知らないところで別な会社に依頼されたことがありました。そうしたら、オスカーが頭から湯気が出るほど怒ってしまって森田を呼べ!”って。今回はしょうがないけれど、次回からは必ず森田を呼ぶようにと、指名が続くようになりました。その流れで、通訳の人を連れて来た本人から“ニューヨークのショーを手伝ってくれ”と言われて、まさか本当に行くことになるとは思いませんでした。彼は本気だったんですよね。まいりました(笑)。」
ニューヨークでのショー。結果を出すことで、認められる。
ニューヨークでの仕事について「ステージの図面をもらって“こういう機材をこれだけ用意してくれ”とお願いして向かったら、向こうの照明の担当者が“こんな機材、今時もう博物館ものだぜ”って言ったんです。服がきれいに見えるようなソフトな明かりを考えて、レンズも細かく指定して。でも、アメリカのスタッフがスゴいなと思ったのは、ショーが終わった時にお客さんの反応が相当よかったので、“オスカーが、わざわざ森田を呼んだ理由がわかるよ”って、ちゃんと認めてくれるんですよね。当時の現地のスタッフのレベルは失礼ながら低かったのですが、結果を出すことで次からは吉村も連れて行くことができ、さらに仕事が早くできるようになりました。余裕でしたね(笑)。」という森田会長です。
オスカーが見せたかったのは、森田さんの『カクテルの妙』でした。
~MATSUDA(マツダ弘光/ニコル)の演出でNYに来ていた長谷川増さんに手伝ってもらうことに~
演出家の長谷川増さんは当時のことを「ニューヨークの会場は、ファッション工科大学のホールでした。現地のスタッフはA班B班のシフトでの対応でしたが、手が遅くユニオンが厳しいため、23時以降は森田さんと二人だけで仕込みをしていました。器材に触ったこともない私が森田さんに怒られながら脚立に上がって、朝まで照明を吊っていたのです。それは怖かったですよ(笑)。旧式の機材で、フィルターひとつ取ってもネジで止めるやつでしたからね。思い出すのは、徹夜してコーヒーを飲んで戻ってきたら、オスカー本人ととても上品なご婦人がいらっしゃって握手をしてくださったんですが、そのご婦人がキッシンジャー氏(ニクソンおよびフォード政権期の大統領補佐官、国務長官)の奥様だったんです。本番ではキッシンジャー氏にもご挨拶ができて、感激でした。」と聞かせてくれました。「ファッションショーの照明は、当時はニューヨークもパリもまだ劇場的な演出で、むしろ日本の方が進んでいたと思います。すでに森田さん、関根さん、吉村さんが実践されていた『洋服とモデルをいかにきれいに見せるか』その『質』を見せていたのです。森田さんは特に色の使い方と組み合わせが素晴らしく、オスカーもそれをニューヨークで見せたかったのだと思いますが、まさに『カクテルの妙』でした。特に白系の組み合わせや、いかに黒をきれいに見せるかは絶妙でした!モデルの肌の『質』をきれいに見せるために、デイライトフィルターにうまくピンクを使われていたんですよね。」
ファッションもABC。それは、1980年代のニューヨークでのショーにおいても、認められていたのです。

衝撃的な出会い。ファッションに、あたらしい感覚とエネルギーが融合する毎日。続きをみる
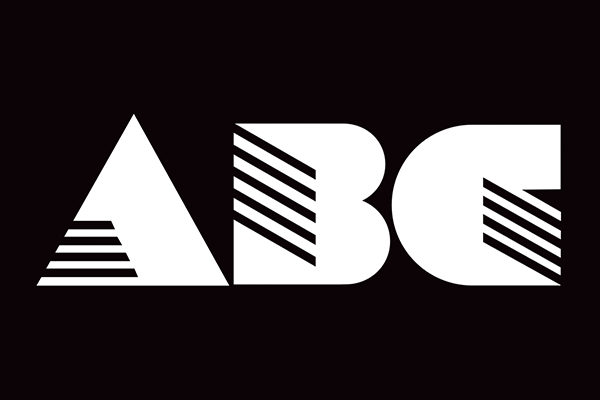
関根 聡(ABC取締役副会長)談
衝撃的な出会い。ファッションに、あたらしい感覚とエネルギーが融合する毎日。
当時、森田が切り拓いてきた時代のファッションとファッションの在り方そのものが、全然違う新しいものになってきたんです。若者にファッションが根づいてきた時代。衣服だけでなく、音楽をはじめ何か全ての新しい感覚とエネルギーが融合して行く状態そのものがファッションとなったというか、若者の今!の考え方、感じ方、例えば、ウッドストックムーブメント、LOVE&PEACEであったりがどんどん表に出てきてファッション全体が活気づき、世の中が感化されて行く瞬間!!とにかくカッコイイ、衝撃的な出会いと創造。個人的にも会社的にもまさに ART・BRAIN・COMPANY 覚醒の毎日でした。
吉村 享洋(ABC取締役社長)談
きっかけは森田。そこに、あたらしい時代のすべて一緒にやって来た。
当時(先駆的な意味で)ABC自体がファッションショーの仕事がメインだったっていうのがあって・・・その頃自分が知っているファッションブランドといったら、「VAN」と「JUN」しかなかったんですが、ABCに入ってから百貨店でいろんなブランドのフロアショーをやり始めて、少しずつ経験していって、ちょうどその時期からDCブランドというか新しいファッションデザイナーが台頭してきて、特に若い人たちが沢山現れて、そこに革命的な演出家四方さん(※四方義朗 ― ファッションプロデューサー・実業家。)という人も出てくる!その時まさに今の時代のあたらしい感覚、価値観を創ろうとするエネルギーが、全て一緒にやって来た!まさにABCにとって、タイムリーに。
久保江 幸雄 氏(元ABC)談
東京コレクション その時代~その瞬間に、一番かっこよくなければならない“場”。
本当に忙しくてツラかったけど、とにかく楽しかった。でも、ツラいのは時間が足りない、それだけです。だって、世の中で一番カッコイイ仕事に参加できているのだから。そこに居て、皆で一緒に創っているんですよ・・・。それも普通のかっこよさじゃなく、個性的な。この音出してるの僕です!いい音でしょうって思って。バーンって音出して、明かりがダーンって点いて、モデルがバーンって出た瞬間のあのカッコよさって。お客さんが、ウォーという感覚が伝わってくるじゃないですか。そこはきれいを表現する現場ですから、ケーブルがきれいに配線されていることは当然、細かいところまできれいにするのが当然。プライドです。
何としてでも良いものを創りたい!そんな思いがあたりまえにありましたね。ABCは、常にベストを尽くすんだと。続きをみる
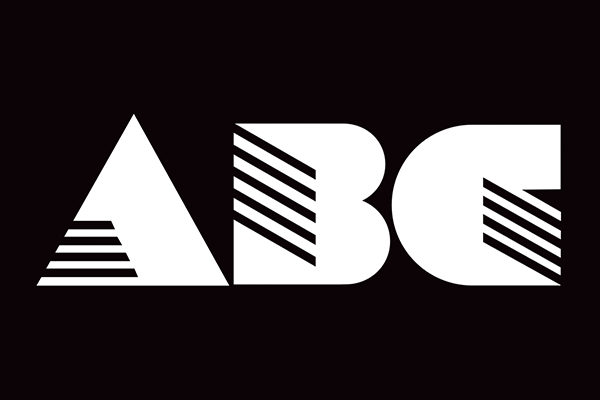
何としてでも、良いものを創りたい。
「東コレ(東京コレクション)の前身となる「東京プレタポルテコレクション」(読売新聞社主催)のショー(運営はSUNデザイン)」では基本仕込み地灯りは3列で、でもそれだけでは不足は明らかで、ABCが依頼されたショー(デザイナー)では、自ら2列足して5列にしていたんです。それを見た他のデザイナー達もその方が良いし、結果いちいち外すのも面倒となって、会期中そのまま常設となりました。なにせ椅子をいちいち片付けて、足場を組んでやっていましたからね(笑)。もう一つ。東コレでは、ABCは(森田がですね)、卓も600万かけて作ったんですよ。このために(これ回収できたのかなあ?)。何としてでも良いものを創りたい!そんな思いがあたりまえにありましたね。ABCは、常にベストを尽くすんだと。」
人と人。信頼の絆。
「東コレ事務局ができて、すぐに呼ばれました。読売のショーの前にも、川久保さんのコム・デ・ギャルソンが単体で代々木にテント建ててやったんです。そこには二瓶さん(※二瓶マサオ ― 照明デザイナー、空間演出家。)のプランで吉村がついていて。で、その二瓶さんが、照明の世界に足を入れるきっかけは森田なんですよ。オスカー・デ・ラ・レンタも二瓶さんがやっていたことありましたね。そして、川久保さんの1982年パリコレからの凱旋ショーは建設途中のフロムファースト、まだ地下がコンクリート打ちっぱなしのところ、そこにステージを作ってやったんですよ。演出が四方さんで、照明音響はABC、関根と久保江でした。」
そして、挑戦。
「そんな流れというか、既に強い信頼の関係が作られていて、結果ABCがいいんじゃない?って声がかかって・・・。でも規模が未だかつてなく大きかったし、その当時のABCにとっては、まさに誰もやったことのない相当覚悟のいる挑戦だったんです。ハードのまとめも含めてやらなきゃならなかったですから。」
吉村メモより。
「初期は照明の仕込み変えをイントレでやったけど、その度に客席の椅子を撤去したりセットしたりで大変な作業!後半はスライド式ゴンドラを常設して作業したけれど、今度は重くて引くのが大変。」「空調設備が十分に完備されてなく、やたら暑かった!逆に夜の転換作業が寒かったこと!その寒い夜に、豚汁の炊き出しやりました。春のショーでは、雪かきから始めることも。」「あるショーでは、客入れの時、事務局控室の館内アナウンスのマイクがONのになったままでスタッフの雑談が会場に流れてしまいました。」
※文中敬称略
初本番!フェーダーを上げた瞬間に!!! それは、まるでノーヘル100kmオーバーの感覚!!!!!... 頭の中は、フラッシュバック&ホワイトアウト・・・・・・・・・ - 関根 聡 -
パリコレという舞台を前に、スタッフは何を考え、どの様に取り組み、何を得たのでしょうか。一部ご紹介します。続きをみる

須崎 和幸(照明部)
2014年、自分が参加したのは JULIUS。ブランドの照明さんと関根さんと自分でGrandMAとMidiキーボードを用いたはしゃぎながらの本番、音源のノリやウォーキング現場の雰囲気を重視したオペは楽しかったですね。設営での現地照明チームとのやり取りも良い糧となり、経験済みだったアジア、中米も含め、照明の仕事が万国共通であることを体感出来ました。
梅田 孝雄(照明部)
UNDERCOVER 2008/02/25 LA CIGALE が初めてのパリでのショーでした。今思えば本番含め緊張でほとんど何も覚えておらず。明かり事で夜中から朝までフレーミングカッターでパネルを切ってました。会場隣のカフェでエスプレッソが美味しかったのと風景が凄く残っています。2回目のアンダーカバーでは、時間ができ食べ歩きざんまいでした。
小野 満(照明部)
24年前の1997年 JUNYA WATANABE の現場でした。パーライトの照明フォーカスに3時間半かかったことに目まいが。物おじせずに日本語でまくしたてれば、目的は同じなので良い結果に仕上がりました。
梨本 愛(音響部)
初パリコレは入社1年が経った2001年頃、UNDERCOVER。衝撃的で驚く事ばかり。建築素材が日本と違い音作りに苦労しました。大理石、天井が高い、天窓が何故あんなに多いのか、音が人に吸われる、という事がこんなに凄い事なのか!と気付くきっかけになりました。そして自分に一言!「食べ物、アートばかりじゃなく現場の写真もっと撮りなよ!」
御須 玲央奈(照明部)
2019年1月、UNDERCOVER の 2019-20AW でアシスタント兼ムービングオペレーターとして連れて行って頂きました。英語も伝わりづらい中、現地照明家達とトラブル対応した事はいい経験です。入社前は、パリコレで仕事をするなんて考えてもみなかったこと。この時の経験のおかげで照明の仕事を続けて行こうと腹を据える事ができ、今に繋がっています。
河村 亮(照明部)
2016年春夏メンズの JULIUS と JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN の2本立てです。片言英語で、フィルターが溶けないようにレンズの種類やシュートの絞り具合を何度も修正しました。やる事・目指すものは日本でも海外でも変わらないと実感できる現場でした。パリは建築デザインと照明の関係が美しく、夜はいつも散歩していました。
森田 紗里(照明部)
2006年ABCに入る前に、UNDERCOVERをはじめ幾つか見せて頂きました。全てが新鮮で、会場の素晴らしさ、日本とは全く違う雰囲気。圧倒されました。UNDERCOVERの時の客入れに使用していた色、最高でした!
小島 達矢(照明部)
旅行の合間に見せてもらった感じです。2回とも、UNDERCOVER と JUNYA だったと思います。何より、会場が歴史的建造物の中でショーが開催されており、雰囲気を見るだけでも楽しめました。2013年1回目の時は、なぜか流れで本番の客電をやることになり、ショーに関わることになりました。これも、パリコレのオペをした実績になるのか??
照明と美術のセットをアート的に見せようとモリちゃんとはちょっとこだわってましたねー続きをみる
![Story 11 80年代 一方[西]では >>> アート的な表現への挑戦が続いていた!](https://a-b-c.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/abc_story_11.png)
野瀬 繁 氏:
演出家。京都を拠点にファッションショーをはじめさまざまな催しを手掛ける。京都をはじめとした神社仏閣でのイベントにおける演出・プロデュースの第一人者。
大阪支社設立以前からABCとの関わりも深い。元ツーインワン・現(株)スタジオマムーン所属。
田辺 尚志 氏:
美術監督。東京12チャンネル(現テレビ東京)に所属した。『演歌の花道』等を手掛ける。同作品の題画は氏の手による。
照明と美術のセットをアート的に見せようとモリちゃんとはちょっとこだわってましたねー
野瀬:東京は、名前の売れたデザイナー・演出家の扱いが多かったけど、西は、無名なデザイナーが多かったから、作品を見せるショーはほとんどなかったんですよ。表に出すために、照明と美術のセットをアート的に見せようと、モリちゃん(森田昭彦会長)とはちょっとこだわってました。平面的な当たりではなく立体的に見せるとか。
演出としては、ベースになる起承転結を考えて、見せ場をどこに持っていくか。頭で衝撃的な演出を一発ぶちかまし、途中ちょっと流す部分もあり、山を持ってきて・・・。
モデルの予算もなかったから背景にダンサー使ったり、小道具に凝ったり、お客さんの目線を衣装周辺で見せるように、とにかくこだわってました。
舞台のベースはもう全部歌舞伎や、っていうのにこだわってまして。
野瀬:私は京都の関係もあって、着物・伝統芸能・歌舞伎とかそういうものがベース、背景にありまして、ほんで田辺さんも、舞台のベースはもう全部歌舞伎やっていうのにこだわってまして、歌舞伎の所作っていうのを背景によく取り入れました。例えばつけうちとかわかる?鳴り物とか、津軽三味線使ったりとか、今で言うミュージカル仕立てというか、通常のファッションショーじゃなくて何か見せる、そんなんにこだわってやってましたね。
松岡(取締役副社長):黒子の衣装を朱に染め、ダンサーが黒子と赤子になり踊って背景になったり、転換要員になったりしてました。
田辺さんのセットは、いつも凄かった!!
森田(取締役会長):田辺さん、あの人のセットはいつも凄かった。安物材料使ってるってクライアントが言い出して、でも文句言うな、明かりが入ったら綺麗になるからと。試しにふわっとつけると本当だった!それでもうOKになった。よその会社はいつも真新しいパネルを持ってくるんだけど、明かりが出ないとか、真ん中は明るいけど、モデルがちょっと歩くと花道にかかる辺が真っ暗になっちゃうとか。もう吊れない、置けない、どうしようもない。パネルをどかせって話になって、スポンサーにどっちを取りますかって言うと、じゃあ、穴開けろとか、そういう風になって来るわけよ。田辺さんはいっつも明かりのことを考えてセットを作ってくれてたよ。田辺さんと武井さん(※東阪企画の故・武井泉会長。Story 5 参照。)がまだ12チャンネルにいた頃からのつき合いだね。
松岡:確かに聞いてくれてました、事前に。ここ仕込めるけどこれでいい?って。
関根(取締役副会長):照明の絵が描いてあるって僕怒っちゃって、若気の至りで。
松岡:激怒してましたもん。それはこっちの考えることやみたいなことですわ(笑)。あれは仕込みじゃなくって、まあ、でも、ここに仕込め!でもありましたけどね(笑)。
関根:当時東京でも、演出家がそういうことを考えずにとんとんと作っちゃってるから、やり直しっていうのも多かったんですよねー。
最終的にはこってこてのエンタメになった。
野瀬:ブライダルも着物のショーも長かったねー。
松岡:1時間以上とかありましたもん。それを飽きささず持たそうと思うと照明も数仕込まな(笑)。フィルターの時代やからあれだけもたそうと思たら、そら舞台も転換しないと単調で持たない。
野瀬:舞台や背景の転換、皆お互い切磋琢磨して演出もいろいろ色づけして。だから最終的にはこってこてのエンタメになった。
※文中敬称略。
※画像は野瀬繁氏提供。
関西で、ちゃんとコーディネーター、音響オペレート、照明プラン、美術デザイン等の項目を作って、請求できるようになったんもモリちゃんがきっかけやで!続きをみる
![Story 12 80年代 一方[西]では >>> 誰もやらないことをやっていた!](https://a-b-c.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/abc_story_12.png)
野瀬 繁 氏:
演出家。京都を拠点にファッションショーをはじめさまざまな催しを手掛ける。京都をはじめとした神社仏閣でのイベントにおける演出・プロデュースの第一人者。
大阪支社設立以前からABCとの関わりも深い。元ツーインワン・現(株)スタジオマムーン所属。
関西で、ちゃんと項目作って請求できるようになったんもモリちゃんがきっかけやで!
野瀬:関西で、ちゃんとコーディネーター、音響オペレート、照明プラン、美術デザイン等の項目を作って、請求できるようになったんもモリちゃんがきっかけやで!
森田(取締役会長):見積りを毎回出しても、みんな、もう要らんとか言うんだけど、「いつもこんだけでやって、今回のセットはこういうセットだからこの金じゃできないよ」と突っ込むと、渋々出すわけだよ。そういうことの繰り返しで。
松岡(取締役副社長):特に関西は、森田が最初にファッションショーを手掛けた頃と一緒で、照明っていうのは電器屋の仕事とか、電器屋が一式なんぼでしょって散々言われ、それを説明して説明して説得して、デザイン料とか取れるようになったんですよね。
森田:そう。だから結果的に、デザイナーがすごい自分の洋服がきれいに見えたって言って来てくれたのね。それは誰かにきれいに見せるために創ってるんだから、はいありがとうございますって、そんな感じだね、俺としては。そこからデザイナーが次も同じところに頼みたいっていうことの繰り返しで、じゃあ、大阪に事務所構えた方がええなあと・・・。
今、お寺使えんのは誰のおかげや思てんねん!という感じやで・・・。
野瀬:お寺っていうのは、もともとイベント用に作った建てもんやから、全部使え言うてくれたのが知り合いの住職(相国寺・金閣寺)、今の仏教界の大ボスですわ。ただ、最初は使わしてくれなかったんですがね。時代的にイベントが全盛期を迎える時、この方から全国に紹介して頂いて、自由に使えるようにして貰ったんですよ。80年代この辺のショーはモリちゃん全部関わってますよ。高台寺、大原三千院。相国寺。そら色々やってますわ。
※文中敬称略。
※画像は野瀬繁氏提供。
ABCの商売道具:
「商売道具というのは、これで飯を食っているもの。だから貸せない。」 その昔、ある道具屋さんに言われて、森田会長が大切にしてきた言葉です。 機材を大切にすることは、 ABCの基本中の基本です。
ABCの商売道具の変遷とその発想の一端が垣間見えるエピソードを幾つか集めました。続きをみる

1975-1976 しゃぼん玉マシーン
40年以上前に、森田は今ではあたりまえになっているしゃぼん玉マシーンを自作した。
1976-1977 切り替えボックス
20kgもあるT6とかくそ重いスライダック6個を差し替えとか。だからあったらいいなってことで、切り替えボックスを自作。
1980 スピナー
これも無かったからつくった。その発想はシステムアートの商品開発に生きている。
1984 60チャン卓 オーダーメイド
定価1千万円のものを、6百万円でつくった。一本のフェーダーで勝負できる機材を。
1986-1987 リックス/LIX(デジタル調光卓)
コンピュータでプログラミングされたリックスも、森田の発想からだった。
1987 12回路の改造ストリップライト
電球が12個に対して3回路だったものを、配線を変えることで12回路に改造した。
1989 GOLDEN SCAN(ABCが初めて買ったムービングライト)
買った方が早い時は、いち早く買った(笑)やりたいことができることを優先して。
1993 ミラーボール
1間玉(直径180cm)ミラーボールもつくった。当時は、日本一の大きさだった。
2002 カクテルパレット
LEDを使ったカクテルパレットを見た森田の直感で、独占契約することに。現在更に照度を増してアップデートされたカラーパレットも扱っている。
2009 「ああ失敗の」ウォータースクリーン(アクアサーモ)
水で字を書くアクアサーモは綺麗だったけど、そこら中を水浸しにして失敗(苦笑)